※性的な描写を含んでいるのでご留意の上でお読みください。
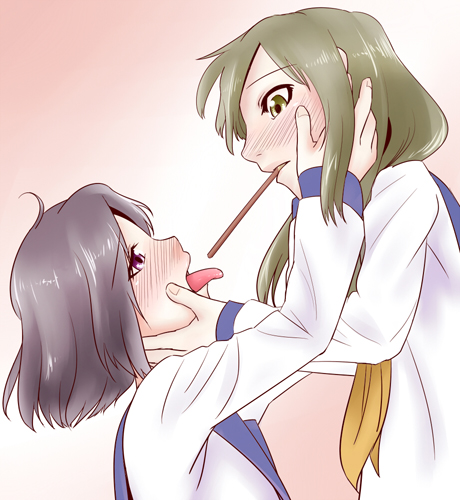
融 解 日 和
彼女の持つコンビニの袋ががさりと揺れ動いた。
いつもの帰り道のこと。
「問題です。今日は何月何日でしょう?」
「十一月十一日でしょ」
「何の日か知ってる?」
「知らない。何かあったっけ」
「今日はね、ポッキーの日だよ」
「へえ、そうなの」
そのコンビニ袋の中身はそういうことか、と納得する。
「そうなの。だから、これから風里んち行ってポッキーゲームしよう」
「……は?」
そう提案した紀穂は本当にあたしの部屋まで押しかけてきた。
「ちょっと! あたしまだ良いって言ってない!」
「まだってことはこれから言ってくれるんだ」
彼女はからりと笑いながら小さなテーブルにポッキーの袋を置く。
「いや、だから」
「んー。とりあえずポッキー食べよう」
定位置のクッションに腰を下ろしてポッキーを開封しはじめた紀穂を見て、あたしはため息をもらした。今日も変わらず、紀穂のマイペースぶりには呆れるばかりだ。
仕方なく自分も同じように袋からポッキーの箱を取り出して開封する。
飲み物も買ってある。相変わらずこういうところは用意がいい。
「風里は極細派?」
「派、ってほどでもないけど」
「身体が細いと好みも細いほうに行くのかな?」
「わけわかんない」
ただそんなに多く食べられないし、甘いのはあまり好きじゃないだけだ。
そんな紀穂はいちご味をぽりぽりと齧っている。
紀穂はあたしとは違って、程よく肉がついていて、バランスのいい身体つきだ。と、以前そのまま言ったら怒られた。
「極細派のアナタは、さっぱりしっかりしているようですごく繊細」
「どこの心理テストよ」
「あたし調べ。風里限定」
「他の味を選んだらどうだったの?」
「知りたい?」
「いや、いい」
そんな他愛のない会話を流しつつ、ぽりぽりと小動物のようにポッキーを齧る。
小袋の半分ほどで手を止め、紅茶で喉を潤す。
「あたしはもういい」
「よし、じゃあしよう」
「そっちの『いい』じゃない!」
「いいじゃん、たまにはこういうのも、ね?」
紀穂がわざわざ普通のポッキーを開封して一本の持ち手側をくわえる。
「チョコ側は譲ったげるから」
「いらない! ていうか、あたし、甘いのあんまり好きじゃない」
「そうだっけ?」
「そうよ」
「んー。……ちょっと待ってね」
そう言って紀穂はポッキーを持ち直し、口の中に入れ、
「ん……」
折らないように丁寧に、チョコレートの部分を舐めしゃぶり始めた。
「ちょっ、何してんの!?」
紀穂の突然の行動を嗜めようとしたが、彼女は止めようとはしなかった。
「あまいの、やなんでしょ?」
そのまま、あたしの部屋に紀穂のたてる水音だけが響く。
この突拍子のなさが紀穂の性格であるのは知っているけれど、本気で頭がおかしくなったのではないかと思った。
でも、頭がおかしくなったのはあたしの方かもしれなかった。
そんな彼女から、もう目が離せない。
愛しそうに蕩けた目も、艶やかに濡れた唇も、上気して斜陽よりも赤い肌も、あどけなくポッキーをつまむ指も、どれもあたしの心をとらえて離さない。
心臓の音が妙に早くてうるさい。
リズムよく混ざる荒い吐息が紀穂のものか、あたし自身のものか、もうわからない。
あたしは何もされていない。紀穂がポッキーのチョコレートを舐め取っているのを見ているだけ。
それなのに、自分が乱されているような、倒錯した感情があたしの中にじわりと広がっていく。
「……はい」
紀穂がただのプレッツェルの棒になったポッキーをあたしの口元に差し出してくる。
「これなら、いいよね?」
プレッツェルはチョコレートの代わりに紀穂の唾液でコーティングされて光っている。それを意識したとたんに、ぞくりとあたしの奥の何かが燃え上がっていく。
直感的に、受け入れてはいけない、とあたしの中から警告が遠く聞こえた。
これを受け入れたら戻れない。もう戻れなくなる。
わからない。
わからない。
わからない。
「……風里」
紀穂が切なそうにあたしの名前を呼んだ。
それだけで、ぷつりと、
そっか、
あたし、
もどりたくないんだ。
ポッキーをくわえた。
折らないように、やさしく、今度はあたしが紀穂の唾液を舐め取っていく。
ほのかに残ったチョコレートの甘さと、紀穂の甘さが、
舌から脳へ、身体へ広がっていく。
しあわせ。
しあわせ。
しあわせ。
しあわせすぎて、しびれていく。
ぞくぞくとしたカンカクにおかされていく。
あたまがおかしくなりそう。
もうおかしくなってる。
それでいい。
もう、それでいい。
紀穂がポッキーのもう片方をくわえる。
ぱり、とプレッツェルを噛み砕く。
その分だけ、あたしに近づく。
ぱり。
近づく。
ぱり。
近づく。
ぱり。
近づく。
ぱり。
彼女が近づくたびにあたしの心が震える。
ぱり。
彼女が近づくたびにあたしの身体が震える。
ぱり。
もうすぐポッキーがなくなる。
ぱり。
早くきて。
ぱり。
はやく!
ぱり――
ゼロになる直前で、紀穂の動きが止まる。
このひと噛みで最後なのに。
自分の呼吸が荒くて、おあずけをくらった犬のようだ。
一センチメートルに満たない距離が果てしなく遠く感じる。
視界を覆い尽くした紀穂は、あたしを見つめたまま動かない。その視線が、「もうわかってるよね?」と言っている。
彼女からいちごの甘い匂いが漂ってきて、あたしの心をさらに焦がしていく。
ああ!
紀穂はいつもそう!
マイペースなくせに、あたしをのせるのはいやに上手くて、
あたしはいつものせられて、
でも、いやじゃなくて、
むしろ、
だいすきで、
ああ、
いじわる!
いじわる!
なのに、
そんなところも、
だいすき。
あたしは最後のプレッツェルを噛んだ。
唇が温もりで融けた。
温もりが口内に滑り込んでくる。
どろりと、甘さと苦さと酸っぱさとしょっぱさが流れ込んでくる。
舌から脳へ、身体へ。
無駄な感覚がなくなる。ひたすら気持ちいい情報だけが走る。
あたしの全部がチョコレートになって融けていく。
しあわせ。
しあわせ。
しあわせ。
「ん、ぷぁっ」
唇が分離する。
あたしと紀穂とチョコレートが混ざった液が垂れて落ちた。薄黒い液はどこか血のように妖しく光った。
ぐらりと世界が揺れた。紀穂に押し倒されたことに気づいた。
そのまま彼女はあたしにまたがって、口から黒い血を垂らす。重力に引かれてあたしの口元に落ちてくる。
血のように暗く、毒のように恐ろしく、蜜のように甘いその液を、舌で受け止める。口内に流れ込んだら、抗わずにこくりと飲み込む。
もっとしあわせになる。
繰り返す。
しあわせ。
しあわせ。
しあわせ。
紀穂の首に手を回し、引き寄せる。
唇が再び融け合う。
絡まる。
しあわせ。
しあわせ。
しあわせ。
悦びにむせびながら、あたしは涙を流す。
あたしたちのつながりは正しいのか、間違っているのか。
こうして彼女と蜜のような時間を過ごすとき、あたしはいつもこうして泣いてしまう。
戻れなくていいと思ったはずなのに、あたしは彼女への申し訳なさでいっぱいになってしまう。
ごめんなさい、と心の中で叫ぶ。
そして紀穂もいつも通り、あたしの頭を撫でながら、さらに優しく愛してくれる。
「風里」
名前を呼ばれる。
「紀穂」
呼び返す。
それだけであたしたちはつながる。
感情が全部混ざり合って、
すべてが快楽に変換されて、
漂白されて、
最後に残った「大好き」の気持ちに、二人で溺れた。
「ふと思い出したんだけど」
二人寄り添ってベッドの側面にもたれ、余韻を味わっていると、紀穂が口を開いた。
「チョコレートって、媚薬っぽい効果があるんだって」
そんな話題を振られても、返答に困る。
「そういえば今日の風里はいつもよりノッてたよね」
「馬鹿!」
再び顔が熱くなる。
「ごめんごめん。でも少しはチョコレート好きになったんじゃない?」
「……だから、言ったでしょ」
あたしは甘いのはあまり好きじゃない。
紀穂だけで、甘過ぎて、すべて満たされてしまうから。
そのまま二人でまどろむ。
日がゆっくりと落ちていく。
あたしは誰にともなく祈った。
永遠なんて望んではいけない。
でも、もう少しだけ、この子を、
この蜜をひとりじめさせてください、と。
(終)
Back